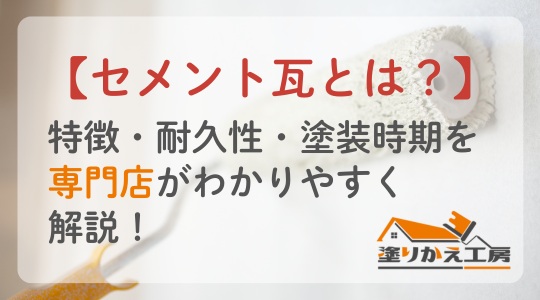 セメント瓦は、1970年代から80年代にかけて、粘土瓦よりも安価で大量生産が可能だったため普及した屋根材です。
セメント瓦は、1970年代から80年代にかけて、粘土瓦よりも安価で大量生産が可能だったため普及した屋根材です。陶器の瓦と比べると、軽量で均一な形状が特徴ですが、表面の塗膜の劣化が進行すると素材が吸水をして強度が落ち、衝撃で割れやすくなるため、定期的な塗装メンテナンスが必須です。
そんなお悩みをお持ちの方に、今回はセメント瓦(モニエル瓦)の特徴や耐久性、メンテナンス方法、そして劣化を放置するとどうなるのかを、わかりやすく解説します!
1. セメント瓦とは?
セメント瓦とは、セメントと砂を型に流し込んで成形した屋根材のこと。
見た目は日本瓦に似ていますが、粘土を焼いて作る「陶器瓦」とは異なり、塗膜によって防水性を保っているのが特徴です。
「モニエル瓦」の名称でも知られていますが、セメント瓦とモニエル瓦は厳密には違うもので、メンテナンスには注意が必要です。
比較的重厚感のある外観が魅力で、洋風の住宅にもよく使われます。
ただし、表面の塗膜が劣化すると雨水を吸い込みやすくなるため、定期的な塗装メンテナンスが必要です。
2. セメント瓦の特徴と耐久性
セメント瓦は高い強度を持ち、風や雪にも強い屋根材ですが、セメント自体には防水性がありません。
塗膜によって水を弾いているため、塗装が劣化すると瓦の内部に水が染み込みやすくなります。
塗装での定期的なメンテナンスが必要な屋根材なのです。
主な特徴
- 重厚感があり、高級感のある外観
- 耐風性・耐寒性に優れている
- 塗膜による防水性能が命
- 定期的な塗装メンテナンスが必要
耐久性の目安
-
瓦本体:30〜40年
-
塗膜:10〜15年
一般的には、上記の様に言われていますが、あくまで目安で、適切な塗装メンテナンスでもっと長持ちさせることが可能です。
セメント瓦は、塗膜が傷んだまま放置すると、水分を吸収した瓦が乾燥・膨張を繰り返し、ひび割れや剥離、さらには凍害(冬場の凍結破損)を起こすこともあるため、プロの定期的な点検が大切です。
3. セメント瓦のメンテナンス方法
セメント瓦のメンテナンスは、塗膜の再塗装が基本です。
次のような症状が見られたら、点検・補修を検討しましょう。
-
瓦の色あせや白化
-
瓦表面のひび割れ
-
塗膜の剥がれやめくれ
-
コケ・藻の繁殖
おおまかな屋根塗装メンテナンスの流れ
1. 高圧洗浄で汚れ・コケ・不要な塗膜等を除去
2. 下地処理・補修
3. 下塗り ※モニエル瓦の場合は特に下塗り材の選定が重要です
4. 中塗り・上塗り
※あくまでおおまかな流れで、状態によっても工程が変わります
塗装の際は、屋根材の状態や環境に合わせて塗料を選ぶと、より長持ちします。
4. 劣化を放置するとどうなる?
-
吸水・凍害による瓦の割れや剥離
-
雨漏りや下地材の腐食
-
屋根全体の強度低下
-
葺き替えが必要になるケースも
放置すればするほど、修繕費用が高くなってしまいます。
また、セメント瓦は現在では流通量が少なくなっています。(モニエル瓦は製造されていません。)
そのため、部分交換が出来ず、補修・修繕で対応できない場合は葺き替えをしなければならなくなる場合も。
10〜15年に一度の塗装が、結果的にランニングコストを抑える方法です。
5. まとめ|セメント瓦は「塗膜の維持」が長持ちの秘訣!
セメント瓦は丈夫な屋根材ですが、「塗膜が命」です。
10〜15年を目安に再塗装を行うことで、耐久性をしっかり保つことができます。
「モニエル瓦かどうかわからない」
「前回いつ塗ったか覚えていない」
そんな方は、まずは塗りかえ工房の診断士による無料屋根点検を受けてみましょう。
早めのメンテナンスが、長く快適に暮らせる家づくりの秘訣です。
塗りかえ工房は、職人直営の塗装専門店です。
長年の経験を積んだお家のプロの診断士が、お客様の大切な建物に最適な提案をさせて頂きます。
外壁塗装や屋根塗装をはじめとした、お家まわりの外装リフォームでお困りの際は、ぜひ塗りかえ工房にご相談ください。
